目 次
数値・金額で、そのものの価値や意義を測定するシリーズです
ビジネスやマーケティングで頻繁に語られるものの、実際にはほとんど数値化されていない(定量化しにくい)要素はいくつもあります。
当社では、それらを数値化してわかりやすくしていこうと試みています。それがこの【計算シリーズ】です。今回は「採用サイト」に焦点を当てます。
「採用サイトなんかなくてよい。マイナビなどの就活サイトを使っているから十分だ」という意見もありますが、果たして本当なのでしょうか?それで十分なのであれば、なぜ、これほどまでに企業は自社の採用サイトを持とうとしているのでしょうか。
採用サイトのある場合、と、ない場合で、金額的な損失はどのくらい違うのでしょうか?
それではレッツゴー。
まずは、採用サイトの利用価値から
「採用サイトなんかなくてよい。マイナビなどの就活サイトを使っているから十分だ」という意見について解説いたしますね。
まず、マイナビやリクナビなどの大手就活サイト(求人サイト)は、求職者への圧倒的な集客力とスカウト機能を備え、多くの応募者を短期間に集めることができます。急いで多くの応募を集めたい場合や、知名度の高い求人媒体を活用したい企業にとっては非常に効果的です。専門の営業担当者によるサポートも受けられ、手軽に利用できる点も強みです。
しかしながら、求人サイトには掲載情報に制限があり、各企業の魅力や雰囲気、ビジョン、社員の声などを十分に伝えきれないというデメリットがあります。そのため、求人サイト経由の応募者は「とりあえず応募してみよう」という気軽な応募が多く、応募後の辞退やミスマッチのリスクも高い傾向にあります。
一方、自社の採用サイトは「その企業に特化した情報発信の場」として、企業文化や社員インタビュー、仕事内容の詳細、職場環境など自由に深く発信できるため、「この会社で働きたい」という強い意欲を持った応募者を獲得しやすいのが特徴です。初期投資や運用コストはかかるものの、長期的には採用コストの削減や採用の質向上、ミスマッチ減少に寄与します。
まとめると、大手就活サイトだけで十分という考えは短期的な応募者数確保には有効ですが、企業独自の魅力や社風を伝えて意欲の高い人材を採用したい場合は自社採用サイトが不可欠であり、両者を併用するのが賢明です。

マイナビを利用している企業は「30,113社」です(2026年卒サイト~2025年3月1日時点)。これは過去最高の掲載社数です。「3万社の中から、自社を選んでもらう!」のは大変な確率です。
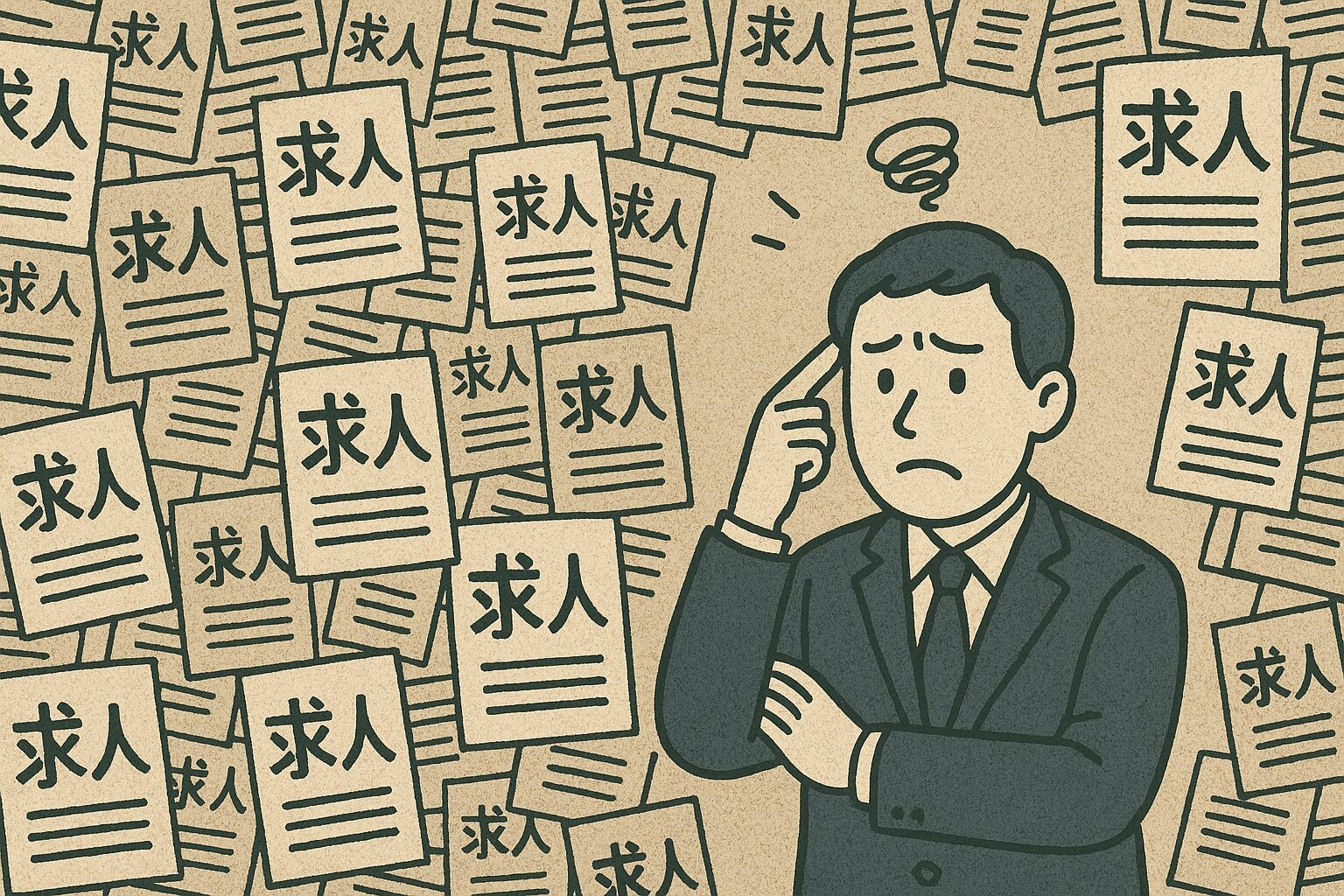
採用サイトがない場合とある場合での損失の種類
採用サイトがない場合とある場合での損失は大きく異なります。採用サイトがないと企業の成長意欲や信頼性が低く見られ、応募者数が減少し優秀な人材を逃す可能性が高くなります。
その結果、かえって採用コストが増加し、採用の効率が悪くなり、最終的に人材不足やミスマッチによる早期離職のリスクも増えます。
一方、採用サイトがあると企業の魅力や情報を効果的に伝えられ、応募者数が増加し、中長期的な採用コストの削減につながります。
採用サイトがない場合の主な損失要因は以下です。
- 企業の成長期待や信頼感の低下で応募意欲減少
- 求人情報の入手難や連絡の取りづらさによる応募機会損失
- 応募者数の減少による人選の余裕不足と採用競争力の低下
- 採用活動の手間とコスト増加、採用難度の上昇
特に若手人材獲得での機会損失は大きく、他社に流れてしまうリスクも高いです。採用サイトは長期的な投資として、求人媒体や広告費の節約にも役立ち、効率よく優秀な人材を採用可能にします。
これらの点を踏まえ、採用サイトの有無による損失の差は応募者数や採用成功率に直結し、場合によっては数百万円以上の採用コスト増加や人材確保の機会損失につながると考えられます。
採用サイトがない場合の採用機会損失率を具体数値で
- 求職者の約80%が応募前に企業の採用サイトやコーポレートサイトを見ており、サイトがないと大きな情報不足や信頼感低下が生じるため、採用機会の約80%が損失される可能性があると言われています。
- 企業のホームページや採用ページが存在しない場合、82%もの求職者が応募意欲が下がると回答しており、これが機会損失に直結しています。
- また、中途採用に特化した採用サイトがない場合、71.3%の求職者が「必要な情報が見つからず調べる意欲が下がる」と答え、約60%の転職者が「応募に至らない」「入社を決めきれない」といった意思決定への悪影響も報告されています。

採用サイトがないことによる採用機会損失率はおおよそ70%以上、多い場合は80%以上に上ると考えられます。つまり、採用サイトがないだけで、求職者の7割から8割が応募意欲を失い、実際の採用につながる機会を多く逃してしまう大きな損失となるわけです。
採用サイトを使って、応募後の辞退やミスマッチのリスクを減らす方法
① 業務内容や企業文化を詳しく、かつリアルに発信する
募集要項だけでなく、仕事内容の詳細や1日の業務フロー、働く環境、社員のインタビューや体験談、社風のネガティブ面も含めた正直な情報を掲載します。これにより、求職者が入社後の現実を予測しやすくなり、「思っていたのと違う」というズレを防ぎます。
② 採用基準・求める人物像を明確化し、評価基準を共有する
採用基準や面接の評価方法を明文化して面接官間で共有し、適性検査や構造化面接の導入で評価のずれを減らします。これにより、企業が本当に求める人材を見極めやすくなります。
③ お試し入社やインターンシップの活用
入社前に現場体験やカジュアル面談の機会を設けることで、双方が働くイメージを持ちやすくなり、ミスマッチの削減につながります。採用サイトを通じて募集します。
④ RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)の実践
仕事の良い面だけでなく過酷さや困難も正直に伝え、現実的な情報開示を行うことで、入社後のギャップを減らし離職率の低下を促します。
採用サイトの有無 数的比較表
| 比較項目 | 採用サイトあり | 採用サイトなし |
| 応募数 | 採用サイト導入で応募数が +140%〜+180%増加(例:月20件→48件) | 求人媒体のみで応募数はやや固定(例:月20件) |
| 採用コスト | 採用サイト初期費用+月運用費約20〜50万円。長期的には広告費30%以上削減。 | 求人媒体の掲載料やエージェント手数料で年間数百万円以上かかる場合も多い。 |
| 内定辞退率 | 約15〜20%(詳細情報で入社意欲が高まり辞退減少) | 約30〜40%(情報不足により入社辞退多発) |
| 採用後の離職率 | 約10〜15%(企業理解向上で早期離職減少) | 約25〜35%(ミスマッチによる早期離職多発) |
| 離職コスト | 離職による再採用・教育コストを年約20〜40%削減 | 離職増により再採用・研修コストが膨れ、合計で年間数百万円増加のケースも。 |
具体的事例
- 飲食業30名規模の企業で、採用サイトを整備し応募数が約1.8倍に増えた事例があります。
- 採用コストは初期構築に数十万円~、運用費は月数万円〜数十万円かかるケースがありますが、広告依存を減らし長期的な費用対効果が期待できます。
- 内定辞退率・離職率ともに、企業情報の充実によるミスマッチ減少で20〜30%程度改善されると想定されます。
結 論
採用サイトのROI(対投資利益)は、1,200万円
ROIとは、投資した費用に対してどれだけの利益が上がったかを示す指標です。
以下、今回の計算式です。採用者1人あたりの売上貢献やコストが想定できると、さらに精度が上がります。
採用サイト投資のROI試算に必要な仮定
- 投資額(Investment)
- 採用サイトの初期制作費用
- 運用・更新費用(月額または年間)
- 採用関連広告費等(もしあれば)
- 採用担当者や関係者の工数コスト(人的コスト)
- 得られる利益(Benefit)
- 採用件数の増加による売上貢献
- 内定辞退率・離職率の低減によるコスト削減効果
- 採用効率向上による採用コスト削減(金額換算)
- 離職コスト(再採用・教育コスト等)の削減額
- 期間
- ROIを計算する対象期間(通常1年など)
ROIの基本計算式 ROI(%)=(採用者数増加数×1人あたり年間利益貢献)+コスト削減額−投資総額/投資総額×100
| 項目 | 数値例 |
| 投資総額(初期+年間運用) | 500万円 |
| 採用者数増加 | 5人 |
| 1人あたり年間利益貢献 | 300万円 |
| コスト削減額 | 200万円 |
仮定数値を代入した場合の利益計算:=(5×300万円)+200万円-500万円=1,200万円
ROIは、支出した費用に対して、結果、どれだけの利益が得られたかを割合で示す指標です。採用サイトへの投資(いくらかけて採用サイトを作ったか)も、この枠組みで費用対効果を明確化できます。仮定の数値は業界・企業規模により変わるため、具体的なシミュレーションでは自社データに基づいた仮定を用いることが望ましいです。
