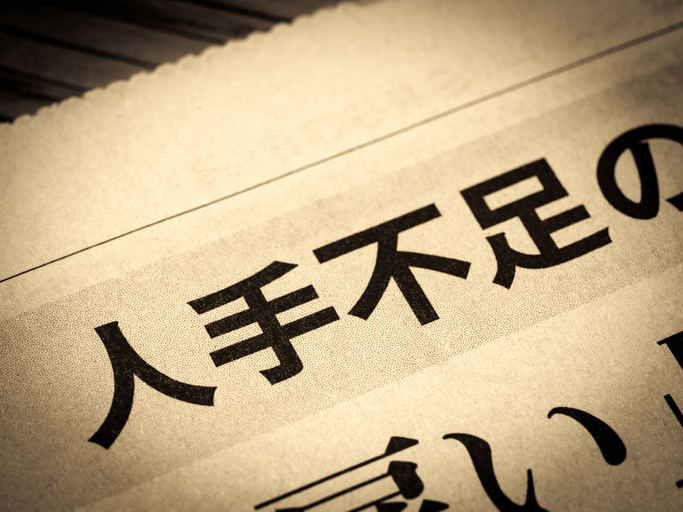
目 次
人手不足が原因で発生する企業の年間経済的損失は、約16兆円
企業の人手不足が原因で発生する年間の経済的損失は、直近の推計で約16兆円にも達しています。
最新の22年度の県民経済計算でみますとと、茨城県(14兆円)を上回り、静岡県(18兆円:人口約350万人|自動車などの産業集積県)の総生産に迫る規模の損失額です。
人手不足の現在の状況
全体規模と具体的影響
- 2024年の日本全体で人手不足による「機会損失」(本来得られるはずだった売上や事業利益の未達成額)は約16兆円と推定されています。
- この額は日本の名目GDPの約2.6%にも相当し、5年前(2019年)の約4兆5000億円から大幅に拡大しています。
- 関連して、特に非製造業(宿泊・飲食・介護など)では、そのうち約13兆円の損失が発生しており、自動化や効率化が進みにくい分野で営業機会逸失が大きくなっています。
倒産や経営悪化の実例
- 2024年度は人手不足を直接要因とした倒産が350件(負債1,000万円以上規模)発生し、統計開始以来最多となりました。
- 倒産に至るケースでは、十分な人員確保ができず生産や営業が縮小、残業・外注費増加で利益率が悪化し、結果として月数十万~百万円単位の赤字が慢性的に発生する状況も珍しくありません。
- 倒産に至らずとも、建設・サービス・運輸など人手集約型産業の中小企業は「人手不足=営業縮小からの恒常的赤字拡大」の傾向が強く、資金繰り難・人件費高騰と併せて負のスパイラルに陥っています。
参考(業種別や企業規模)
- 建設業・物流・サービス業では特に影響が大きく、2024年上半期でも人手不足倒産件数の8割が小規模事業者(従業員10人未満/資本金1,000万円未満)で発生しています。
- サービス業の例では、現場人員の確保ができず営業時間やサービス提供数を縮小、その結果、年間売上が2%減少するなどの具体事例も確認されています。
このように、人手不足は単に人件費や離職コストの増加という「直接的な赤字」だけでなく、大規模な「営業機会損失」という形で、数兆円単位の経済的損失を企業・社会全体にもたらしています。
人手不足による赤字の主な算出項目
人手不足による赤字の主な算出項目には、以下のような内訳があります。
主な算出項目
- 人件費の増加:残業手当や外注コスト、一時的な高額人材の採用費が増加し、売上に対する人件費率・労働分配率が上昇します。
- 採用・離職関連コスト:欠員補充のための求人広告・採用活動費、教育・研修費、既存従業員の早期離職にともなうコストが発生します。
- 生産性・営業効率の低下:人手不足により業務効率や営業稼働率が下がり、一人当たり売上高が減少します。
- 機会損失:受注や案件・作業依頼の取りこぼし、営業時間やサービス提供枠の縮小により、本来得られるはずだった売上が失われます。
- 社会保険料等の間接的な人件費:増加する人件費に比例して、社会保険や法定福利費などの負担も膨らみます。
- 業務改善・外部委託費用:人手不足を補うための自動化投資費用や、外部委託コストが増大します。
人手不足による赤字額
結論から言うと、人手不足の赤字は「欠員による粗利の取りこぼし」+「割増残業」+「離職・採用の上振れ」+「品質・遅延損失」を積み上げると現実的な金額が算出できます。ざっくりではありますが、以下に計算式と金額を示します。
基本計算式(概算のフレーム)
- 欠員による粗利の逸失= 欠員数 ×(一人当たり年商 × 粗利率)×(欠員日数÷365)× 取りこぼし率※「取りこぼし率」は、需要が後で回復しない分(0〜1)。ボトルネック職種は高めに。
- 割増残業コスト= 残業対象者数 ×(超過時間/⽉)× 期間(月) × 時間単価 × 割増率
- 離職・再採用コスト= 追加離職者数 × 年収 × 置換係数(一般に年収の20〜40%で概算)
- 紹介会社手数料(使う場合)= 紹介人数 × 年収 × 紹介料率(例:20〜35%)
- 品質・やり直し= 増加件数 × 1件あたり不良コスト
- 納期遅延・違約金= 違約金・減額分の合計
参考サンプル(従業員数:50名|欠員5名|90日として)
- 年商/人:2,000万円|粗利率:35%|取りこぼし率:60%
- 残業対象10人|超過20h/月×3ヶ月|時間単価3,000円|割増0.25
- 追加離職1人|年収600万円|置換30%
- 紹介2人|紹介料25%
- 不良10件×5,000円
- 遅延30万円
計算結果(概算)
- 粗利取りこぼし:約5,178,082円
- 割増残業:450,000円
- 離職・再採用:1,800,000円
- 紹介手数料:3,000,000円
- 不良:50,000円
- 遅延:300,000円
▲ 損失額の合計 約10,778,082円(約1,078万円/90日)

人手不足で増える固定費と変動費の具体例
人手不足になると企業では「固定費」も「変動費」も増加しやすくなります。具体例は以下のとおりです。
固定費の具体例
- 正社員の基本給や賞与:固定的に発生するため、人手不足時も一人ひとりの基本給が増えることは少ないですが、補充困難で追加雇用を余儀なくされると全体額が膨らみます。
- 法定・法定外福利厚生費:社会保険料、福利厚生費、通勤交通費など、在籍人数が維持されると継続的に増加します。
- 管理部門の人件費・オフィス家賃:人手不足対策で採用担当や間接部門を強化する場合、毎月費用増に直結します。
- 教育研修費:新規採用や配置転換の増加で年間計画的に支出されやすくなります。
- 人手確保のためのツールやRPA等IT投資:外部サービスやサブスクリプション契約は毎月の固定出費となるケースが増加しています。
変動費の具体例
- 残業手当・深夜手当:人手が足りず従業員の残業や休日出勤が常態化し、業績や稼働変動に応じて金額増加します。
- 外注費・派遣社員・短期バイトの費用:繁忙期や欠員補充を外部人材で対応した場合、必要に応じて都度費用が発生し変動費として計上されやすいです。
- 採用広告や人材紹介手数料:募集活動を強化する分、応募数や採用件数に比例して変動します。
- 成果報酬・歩合給:営業職などで成果や労働量に応じて追加支給されます。
- 製造原材料費・販売手数料:人手不足の結果、外注化や協力会社を多用すると、業務量分増減します。
- 外部委託・アウトソース業務の増加:代替手段としてスポット依頼やプロジェクト単位費用が変動します。
このように、人手不足が深刻になると固定費は「人材維持・恒常的コスト」の拡大、変動費は「残業・外注・採用強化等の臨機応変な追加コスト」の増加として現れてきます。
人手不足になると、なぜ社会保険料や福利厚生費の支払いが増えるの?
人手不足が深刻化すると、企業では社会保険料や福利厚生費の支払いが増える傾向があります。主な理由は以下の通りです。
- 人手不足を補うために賃上げや待遇改善を行うと、一人あたりの給与水準が上がり、それに連動して社会保険料(健康保険・厚生年金など)の会社負担分も増加するからです。
- 社会保険適用の範囲が拡大したり、パート・アルバイトなど非正規雇用の加入者が増えることで、法定福利費の総額も増えるからです。
- 福利厚生費も、人材確保や定着率向上のためレクリエーションや手当などの支給拡大によって上昇する傾向にあります。
慢性的な人手不足が続くと、賃金・社会保険料・福利厚生費のいずれも企業の固定費として増加しやすくなります。
人手不足倒産企業、急増。採用活動、待ったなし
いまは16兆円の損失に驚いている場合ではありません。「人手不足が原因で倒産する企業」が今後急増すると心配されています。いまのうちに手を打っておきましょう。採用に躊躇している時間は残されていません。※採用以外では、ソフトウエア投資(生産性改善)という一手もあります。
